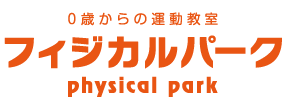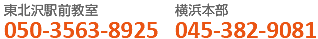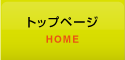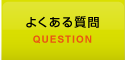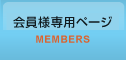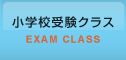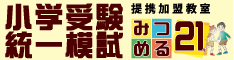「落ち着きがない」「集中できない」…親の悩みは深い
「イスにじっと座っていられない」
「宿題を始めてもすぐにやめてしまう」
「授業中に立ち歩いてしまう」
ADHDや多動傾向のある子どもにとって、
“落ち着き”や“集中力”はよく聞かれる課題です。
しかしこれは 性格や努力不足ではなく
、脳と体の発達特性 が背景にあります。
なぜ落ち着き・集中力が育ちにくいのか?
- 前頭前野(感情や行動をコントロールする脳)が未発達
- 感覚が過敏/不安定で刺激に引っ張られやすい
- 失敗体験の積み重ねで「どうせできない」と自信を失いやすい
単に「座りなさい!」と叱っても改善は難しく、
脳と体に合ったアプローチが必要です。
・教室での取り組み
アプローチ①:ビジョントレーニング
「目の使い方」を整えることは、
落ち着きや集中の土台になります。
- 指やペン先をゆっくり追視する
- 近くと遠くを交互に見る
- 遊び感覚で左右に動くものを目で追う
視線が安定すると、学習や生活における
「集中して取り組む力」が伸びていきます。
アプローチ②:感覚統合(Sensory Integration)
体の感覚をバランスよく働かせることで、心も安定します。
- ブランコやバランスボードで前庭感覚を刺激
- ボールキャッチで手と目の協応を育てる
- クロス運動で左右の脳をつなぐ
感覚統合(Sensory Integration)は、
落ち着きと集中を高める重要な基盤です。
アプローチ③:小さな成功体験の積み重ね
「1分できたら大成功!」のように小さな目標を設定すると、
子どもは「できた」という感覚を持ちやすくなります。
この小さな成功体験の積み重ねが、やがて
「集中できる自分」への自信 に変わります。
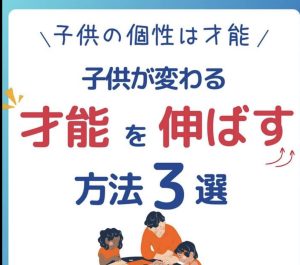
実例:Hくん(年長)のお話
Hくんは、折り紙や工作を始めても1分と続かず立ち歩いてしまう子でした。
保護者も「どうして座っていられないの?」と毎日悩まれていました。
そこで教室では、
- ビジョントレーニングで普段使っていない脳を活性化
- 感覚統合(Sensory Integration)で体と心を整える
- 「2分できたら花丸!」と小さな成功を積ませる
という方法を続けました。
3か月後には…
- 制作に10分以上集中できるようになった
- 授業中の立ち歩きが減り、先生から「落ち着いて聞けるようになった」と言われた
- 宿題もスムーズに取りかかれるようになった
という大きな変化が見られました。
・大学特別講師としての視点
「落ち着き」や「集中力」は、
叱って座らせて育つものではありません。
ビジョントレーニング
・感覚統合(Sensory Integration)
・小さな成功体験――。
これらを通して脳と体を整えることが、最も自然で効果的な方法です。
・まとめ
ADHDや多動傾向の子どもに必要なのは、
特性を理解した上で「できる工夫」を積み重ねること。
落ち着きや集中力は、正しい関わりで必
ず伸ばしていけます。
👉 お子さんに合った方法を知りたい方は、体験レッスンで実際にお試しください。