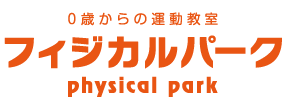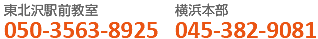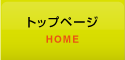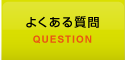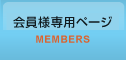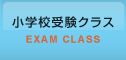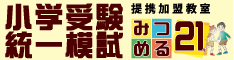「勉強より大切な力」って何だろう?
──そんな問いの答えが、いま注目されている
“非認知能力”です。
やり抜く力・共感・自己コントロール力など、
テストでは測れないけれど、
人生を支える“生きる力”のこと。
この力は、家庭や運動教室の中で
自然に育てることができます。
家庭で育てる5つのコツ
子どもの非認知能力は、
毎日の生活の中で「少しの関わり方」を変えるだけで
ぐんと伸びていきます。
| 育てたい力 | 関わり方のコツ | 効果のポイント |
|---|---|---|
| やり抜く力 | 「もう1回だけやってみようか」 | 小さな挑戦が「続ける力」を育てる。 |
| 感情コントロール | 「今どんな気持ち?」と聞く | 言葉にすることで感情を整理できる。 |
| 自己決定力 | 「どっちにする?」と選ばせる | 小さな選択が自己肯定感につながる。 |
| 共感力 | 「ありがとうリレー」を家族で | 感謝の習慣が相手理解の力を育てる。 |
| 集中力 | 10分間の“ひとつだけ時間” | 没頭する経験が集中力の基礎になる。 |
👉 ポイントは「親が正解を与えすぎないこと」。
失敗も学びのチャンスとして、
“見守る勇気”が大切です。
運動教室で育つ非認知能力
運動には「心を整える力」があります。
体を動かすことで脳幹が刺激され、
情動や集中のコントロールにも直結します。
| 育てたい力 | トレーニング例 | 育つ理由 |
|---|---|---|
| 挑戦力 | 跳び箱・鉄棒 | 「怖いけどやってみる」経験が自己効力感に。 |
| 協調性 | ペア運動・リレー | 相手に合わせる力=社会性を育てる。 |
| 感情調整力 | 音楽リズム運動 | 自律神経を整え、落ち着きや集中を促す。 |
| 集中力 | ビジョントレーニング | 目の動きの制御が注意力の基盤になる。 |
| 自己理解力 | 振り返りタイム | 自分の行動を言葉にし、客観性が育つ。 |
運動と非認知能力の関係
近年の研究でも、
「身体活動が前頭前野を活性化し、
感情や行動の自己調整を高める」ことが
明らかになっています(Harvard University)
つまり、
“体を動かすことが心を育てる”。
運動は「心の筋トレ」でもあるのです。
家庭と教室をつなぐ工夫
-
「できた!」を言葉にする習慣
-
チャレンジシートで“見える成長”を記録
-
親子で「今日のすごい」を1つずつ発表
この3つを意識するだけで、
非認知能力の成長スピードは変わります。
非認知能力は、生まれつきではありません。
「関わり方」で育てる力です。
家庭と運動の両輪で、
「できた!」と「できそう!」を増やしていく。
それが、子どもの一生を支える土台になります。
🏫 フィジカルパークでは
子どもの「見る・動く・感じる力」を通して、
非認知能力を育てる運動プログラムを実践しています。
お子さんに合ったトレーニング体験は
こちらから👇
ビジョントレーニング&プレイセラピー*フィジパプログラムを体験*