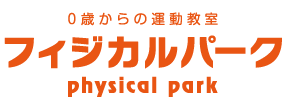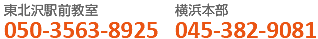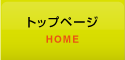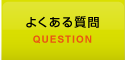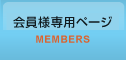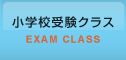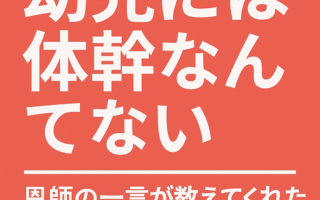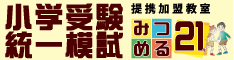「幼児には体幹なんてない」
私が大学時代にお世話になった、元日本体育短期大学学部長であり、
日本体育大学児童教育学部の恩師が、あるとき、静かにこう言いました。
当時はその意味がわからず衝撃を受けました。
けれど今、教室で子どもたちの動きを見つめるたびに、
その言葉の深さを実感します。
今回は、恩師の言葉をきっかけに「幼児の体幹とは何か」
「鍛えると育てるの違い」を、感覚・神経・遊びの観点から解説します。
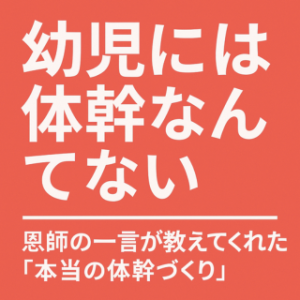
1. 「幼児には体幹なんてない」──その言葉の背景
この言葉は、筋トレ的な「体幹信仰」への警鐘でした。
幼児期(0〜6歳)は骨格も神経もまだ未熟で、
“体を支える筋肉構造そのものが未完成”です。
そのため、「体幹を鍛える」という大人の概念は、
この時期の発達に当てはまりません。
本来この時期に育てるべきは、筋肉ではなく——
「体を感じる力」「姿勢をつくる感覚の回路」
なのです。
2. 幼児の体幹は“感覚システム”で支えられている
姿勢保持に使われる「感覚の柱」は以下の3つです。
| 感覚 | 内容 | 発達の役割 |
|---|---|---|
| 前庭覚 | 体の傾き・回転・スピードを感じる | バランス・空間認知の基盤 |
| 固有覚 | 筋肉や関節の伸び・力加減を感じる | 姿勢保持・運動調整 |
| 触覚 | 皮膚からの圧や刺激 | 安心感・身体イメージ形成 |
これらの感覚を脳が統合して、「いま自分の体はどうなっているか」
を無意識にコントロールしているのです。
つまり、“感じる力”が“支える力”より先に育つ。
だからこそ「体幹を育てる=感覚を育てる」なのです。
3. 「体幹を鍛える」風潮の落とし穴
最近ではSNSや教育現場でも「体幹を鍛えよう」
という言葉をよく目にします。
しかし、幼児にとっては静的姿勢の保持(プランクや長座姿勢)は、
発達的に逆効果になることがあります。
-
筋肉への過負荷
-
感覚入力の不足
-
動く経験の減少
-
「できない=ダメ」と思わせる否定感
幼児にとって大切なのは、“止まる”ことではなく、
“動きながら感じること”です。
4. 「育てる体幹」とは何か
恩師の言葉を借りるなら、
「体幹は鍛えるものではなく、遊びと感覚で自然に育つもの」
ということ。
そのためには、動きと感覚をつなげる経験が欠かせません。
たとえば――
-
ブランコで揺れる
-
坂道を転がる
-
ロープを登る
-
平均台を渡る
-
砂場で踏ん張る
こうした“揺れ・ねじり・転がり”を伴う動きが、
前庭覚・固有覚・触覚を自然に育ててくれます。
5. まとめ──恩師の言葉を現代に生かす
「幼児には体幹なんてない」
それは、筋肉ではなく“神経と感覚”を育てなさいという、教育者としての深いメッセージでした。
体幹を育てることは、姿勢だけでなく、
集中力・運動能力・情緒の安定にもつながります。
筋肉よりも、感じる力を。
できることより、感じ取る経験を。
それが、今の子どもたちに必要な「本当の体幹づくり」です。
🎯 親子で「感じる力」を育てよう
フィジカルパークでは、0歳からの個別運動レッスンやオンライン体験を通して、
お子さまの体の使い方・見る力・感じる力を総合的にサポートしています。
👉 体験レッスンを予約する
https://peraichi.com/landing_pages/view/hh5gh