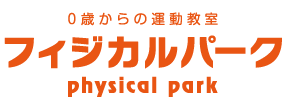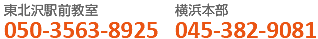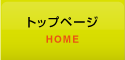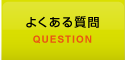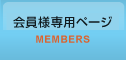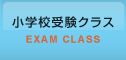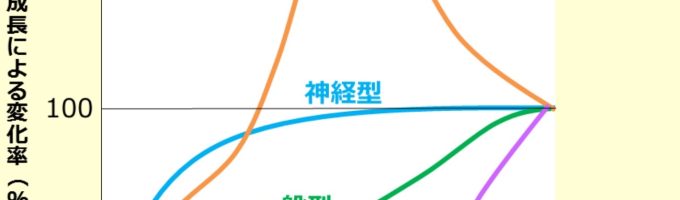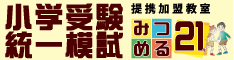■ 1. 「○歳だからできる」は本当?
子どもの成長を語るときに、よく耳にする言葉があります。
「3歳までが脳のゴールデンエイジ」
「6歳で運動神経が決まる」
「思春期前が勝負」
どれも“もっともらしい”響きですが、実はその多くは
科学的根拠があいまいなまま、広く信じられているのが現状です。
■ 2. スキャモンの発達曲線とは?
日本の保健体育の教科書にも登場することがある「スキャモンの発達曲線」。
これは1930年代、アメリカの解剖学者スキャモン(Scammon)が示した
「人間の成長を4つの型に分けた曲線」です。
-
神経型:脳・神経の発達(幼少期に急成長)
-
一般型:身長・体重など(思春期に急成長)
-
リンパ型:免疫系(小学生時代にピーク)
-
生殖型:性ホルモンや第二次性徴(思春期以降に発達)
ただし、これはあくまで「体の大きさ」など量的変化のモデル。
学習能力や運動スキル、心の発達とは別物なのです。
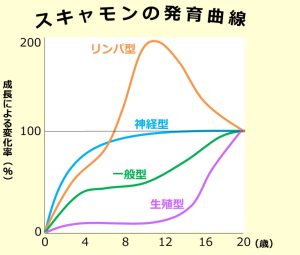
■ 3. ゴールデンエイジ神話の誤解
「ゴールデンエイジ」はもともと、スポーツ指導の世界で使われた言葉です。
「9〜12歳ごろは神経系の発達が完成に近づき、技術習得に最も適した時期」
とされてきました。
しかし、近年の研究では、
-
神経の可塑性(=いくつになっても変化できる力)は大人にもある
-
運動スキルは年齢よりも「経験量」「環境」の影響が大きい
ということが分かってきています。
つまり、「この時期を逃したらもう遅い」という考えは根拠が弱い神話なのです。
■ 4. 日本の教科書と海外の違い
日本では中学校の「保健体育」教科書の一部で
スキャモンの発達曲線が紹介されることがあります。
ただし、それは「体の成長を理解するため」の参考図であり、
発達理論として強調されているわけではありません。
一方、海外では「ゴールデンエイジ」という言葉はあまり使われず、
代わりに “sensitive period(感受性期)” や
“windows of opportunity(発達の窓)” といった表現が用いられています。
つまり、海外では**「年齢で区切る」よりも「個のタイミングを尊重する」**発想
が主流になっているのです。
■ 5. 子育てで大切なのは「曲線」より「観察」
スキャモン曲線もゴールデンエイジ理論も、「平均値のモデル」です。
けれど、子どもの発達は平均値ではなく
“その子だけのリズム”で進んでいきます。
大切なのは、「今どんな経験が必要か」
「どんな環境なら伸びやすいか」を丁寧に観察すること。
焦らず、比べず、目の前の小さな変化を見逃さないことが、
何よりの“育ち支援”です。
■ 6. 決めつけず、見守る勇気を
「スキャモン曲線」「ゴールデンエイジ」という理論は、
子どもの成長を理解するための“ヒント”にはなります。
でもそれは、「この子はこう育つはず」という決めつけではなく、
「この子はどう伸びるだろう?」と見守るための地図のようなもの。
子どもの育ちは、年齢ではなく経験と関わりで形づくられていきます。
■ フィジパ式の考え方:発達は「脳 × 体 × 環境」の三位一体
フィジパでは、「目=脳の出入口」として、
視覚機能(見る力)と体の動きをつなげるトレーニングを行っています。
ビジョントレーニングや原始反射の統合、体幹・姿勢・バランスの発達を通して、
お子さんの“学びと運動の土台”を育てています。
👀 新着記事をLINEで受け取りませんか?
フィジパでは、「視覚機能」「原始反射」「体と心のつながり」など、
子どもの発達を専門的に解説する最新記事を配信しています。
✅ 登録無料
✅ 月1〜2回ペースで新着ブログをお届け
✅ 限定チェックシートもプレゼント
📲 LINE登録はこちら
👉 https://lin.ee/VH78z2q