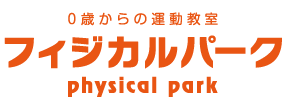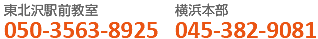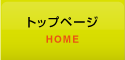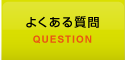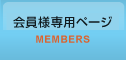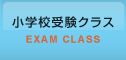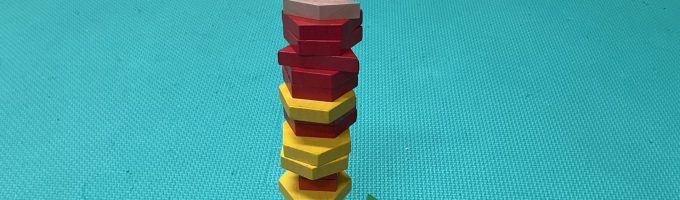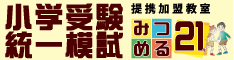子どもの考える力は、教え込むよりも「待つ力」で伸びます。つい「こうすれば早いよ」と口を出したくなる瞬間こそ、ぐっとこらえて見守ることが大切。寄り道や失敗の中に、気づきと成長のヒントが隠れています。
「考える力」は教えるより引き出す
大人の善意のアドバイスが、子どもの考える力を止めてしまうことがあります。答えを先回りして伝えると、子どもは「自分で考える必然」を失ってしまうからです。教室でも、私はまず“待つ”。その間に、子どもは目で状況を捉え、頭で作戦を立て、体で試します。この循環こそ、考える力の土台です。
口を出さないことが育てる力
ブロックが倒れても、逆上がりに失敗しても、すぐに手助けせず見守る。失敗→仮説→再挑戦のサイクルを回すことで、子どもは「どうして?」から「じゃあ、こうしてみよう!」へと自走します。これは考える力の筋トレです。
効率より“寄り道”に価値がある
大人にとって非効率でも、子どもにとって寄り道は発見の宝庫。遠回りの中で仮説検証が起こり、結果として考える力が伸びます。関連の観点は、文部科学省が掲げる「生きる力」にも通じます(
文部科学省公式サイト)。
姿勢よりも“心の姿勢”を見る
夢中で考えているとき、姿勢が崩れたり字が雑になるのは、脳がフル回転しているサインです。できているかより、今“心がどう動いているか”を見取りましょう。考える力は、正しさの強要ではなく、安心して試せる環境から生まれます。
今日からできる見守りのコツ
① 待つ合図を決める
親子で「今は見守るタイム」と合図を共有。子どもが自分で区切れると自走が進みます。
② つぶやき質問を使う
答えを言う代わりに「次はどうしよう?」などのオープンクエスチョンで促す。
③ 失敗の記録をほめる
成功よりも「試した回数」を評価。挑戦のログが考える力の証拠になります。
④ 1日の中に“寄り道タイム”
効率を求めない自由工作・自由読書の時間を意図的に確保。
発達チェックシート🎁 & 無料個人相談のご案内
お子さまの考える力・目と体の連動を家庭で確認できる「発達チェックシート🎁」
を配布中です。
また、教室長による無料個人相談も受付中。
👉 お申込み・ダウンロードは下記からご案内しています。
📍対応エリア:世田谷区(北沢・代沢・代田)/渋谷区(大山町・上原・富ヶ谷・幡ヶ谷) ほかオンライン