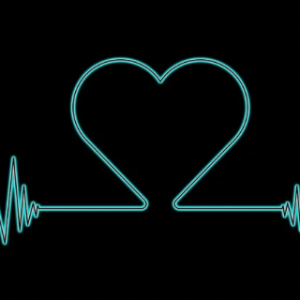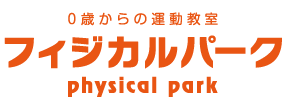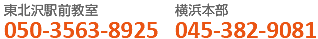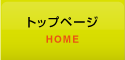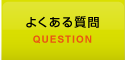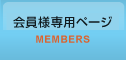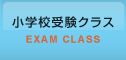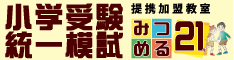子どもの集中力や落ち着きは“音の使い方”で変わります。
教室では、レッスン中はずっと音楽を流し、
視機能(ビジョン)トレーニング時にメトロノームを使って
「安心→集中」の流れをつくっています。
なぜ“音”で集中が変わるの?
「ご飯中に立ち歩いてしまう」
「注意してもすぐ別のことを始める」
「じっとしていられない」
――多くのご家庭で見られる行動は、
言葉の注意よりも“音の環境”を整えるほうが先に効くことがあります。
やさしい音は心とからだを落ち着け、
テンポのある音は活動や集中を後押しします。
フィジパのレッスン設計(音楽とメトロノーム)
フィジパでは、子どもが安心して参加できるよう、
レッスン全体を通してBGMを流しています。
空間にやさしいリズムがあることで、
表情・呼吸・動きが自然に整い、活動に入りやすくなります。
- レッスン全体:やさしい音楽で場を整え、安心して動ける土台づくり
- ビジョントレーニングの場面:メトロノームで一定のテンポを示し、
- 目線・姿勢・動作のリズムを安定させる
言葉で「集中して」と繰り返すのではなく、
音が先に脳とからだのリズムを整えるように設計しています。
脳が音に反応するしくみ(やさしく解説)
人の脳はリズム刺激に反応して状態が切り替わります。
ゆったりした音のときは落ち着きに関わる
脳のリズム(例:アルファ波)が優位になり、
一定のテンポのときは活動・判断に関わるリズム
(例:ベータ波)が高まりやすくなります。
この切り替えを活かすために、
フィジパは「安心をつくる音」と
「集中を引き出すテンポ」を意図的に使い分けています。
家庭でできる音の使い分け
- 朝:少しテンポのあるBGMで“行動スイッチ”を入れる
- 宿題・読書前:一定テンポ(メトロノーム系でもOK)で姿勢と視線のリズムを整える
- 夜:やさしい音で“安心スイッチ”を入れる(音量は小さめに)
お子さんの感覚に合わせて、音量・音色・曲の質感を調整しましょう。
無理に音を乗せるのではなく、心地よさを基準に。
🔜 次回予告(実践編へのご案内)
次の記事では、おうちで使える具体リスト
(音の切り替え/声かけテンプレ/最新のレッスン事例)をまとめてご紹介します。
レッスン中は音楽を、視機能トレーニングでは
メトロノームを――この流れを家庭でも応用できる形にしました。