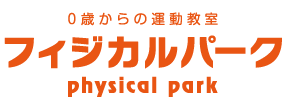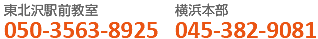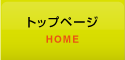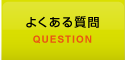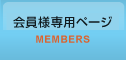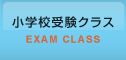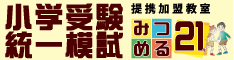子どもの「癇癪」「強いこだわり」で悩んでいませんか?
「ちょっとしたことで泣き叫ぶ」
「順番を譲れない」
「朝の支度が進まない」
こうした姿は決して珍しいものではありません。
しかし大学特別講師として子どもの発達を学び、
教室で多くの子どもを指導してきた経験から言えるのは――
癇癪やこだわりは“性格”ではなく、脳と体の発達のサイン だということです。

・癇癪・こだわりの背景
子どもの脳はまだ発達の途中。
感情をコントロールする「前頭前野」が未成熟なため、気持ちの切り替えが難しいのです。
さらに視覚や空間認知が不安定だと、不安やこだわりが強く表れることもあります。
叱って抑えるのではなく、発達に合った関わり方が必要です。
・効果的な方法:「動と静を繰り返す運動」
教室で実際に取り入れているのが、
**動いて止まる・走って休むといった
「動と静の切り替え運動」**です。
- ジャンプしてピタッと止まる
- 走った後に座って深呼吸
- 模倣体操の後に目を閉じて静止
こうした体験が、脳に“ブレーキをかける回路”をつくり、
- 気持ちを切り替える力
- 注意を向け直す力
- 自分で落ち着ける力
を育てていきます。
・実際の変化(年中さんの例)
ある年中さんは、園で順番を譲れず癇癪を起こすことが日常。
そこで週1回の切り替え運動を3か月継続した結果、
- 順番を待てるようになった
- 泣いても深呼吸で気持ちを整えられるようになった
- 朝の支度もスムーズに進むようになった
という大きな変化が見られました。
・大学特別講師としての視点
大学で保育者を育成する授業でもお伝えしていることですが、
「癇癪やこだわりを“行動の問題”として叱っても改善は難しい」
というのが現実です。
必要なのは、脳と体の発達を理解したうえで、
遊びや運動を通して“切り替える力”を育てること。
それが子どもの安定した心をつくります。
・まとめ
癇癪やこだわりは、発達の過程で現れるサインです。
「動と静の切り替え運動」を取り入れることで
、日常の困りごとは確実に改善していきます。
👉 お子さんの癇癪やこだわりでお困りの方へ
公式LINEに登録いただければ、個別相談も可能です。
ぜひお気軽にご登録ください。