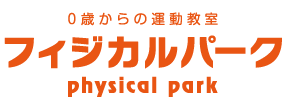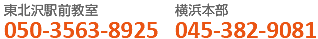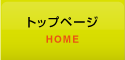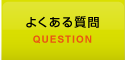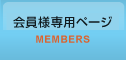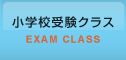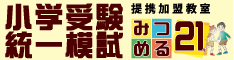青木裕子さんの記事から考えたこと
「世間の正解ばかり選んできた」――
元アナウンサーの青木裕子さんが、小学校最後の夏休みを終えた
息子さんの将来について語った記事を読み、ハッとしました。
偏差値の高い学校、知名度のある企業という“正解の道”。
安心はありますが、それが本当に自分のやりたいことにつながるのか…。
そんな彼女の言葉に、指導者としても深く考えさせられました。
私たちもつい、子どもに「正解」を歩ませたくなります。
でも本当に大切なのは、正解を選ぶことではなく、自分で気づき・選び・挑戦する力 を育てること。
視覚機能と脳発達がつくる“未来の土台”
近年の研究では、その力の土台に「視覚機能」と「脳の発達」が深く関わっていることが示されています。
◎ 視覚注意は学習の土台になる
Nature(2025)の研究では、乳児期の「見る力(注視・注意の切り替え)」が、その後の言語力や記憶力を予測することが報告されています。
◎ 視覚と運動は6歳までに急成長
UNCの研究では、6歳までに視覚と運動のネットワークが急速に発達し、集中力や問題解決力の基盤をつくることが明らかになっています。
◎ スクリーンタイムが脳に与える影響
米国の小児病院の報告では、幼児期にスクリーン時間が長いと、注意力や読み書きに関わる脳領域の発達に影響が出るとされています。
☆つまり「どう見るか」「どんな環境で育つか」が、
子どもの未来を大きく左右するのです。
親としてできる工夫
日常生活の中で取り入れられる工夫もあります。
・色や形を比べる遊び
・ボールや風船を使った「見る×動く」遊び
・スマホやタブレットの時間を減らし、実物を見て触れて体を動かす体験
こうした工夫はすぐに取り入れられます。
でも実際には「毎日続けるのは大変」「これで合っているのか不安」という声も少なくありません。
一人で抱え込まなくてもいい
子どもの「見る力」や「脳の発達」を支えるには、継続と工夫が欠かせません。
だからこそ、外の視点や専門的なサポートがあることで安心につながります。
実際に保護者の方からは、
「家庭でもやれることはあるけど、専門家に見てもらえると安心」
「子どもに合った方法を教えてもらえるから続けやすい」
といった声をいただいています。
外の力を借りるのは弱さではなく、子どもの未来を支えるための“投資”だと私は考えます。
青木裕子さんの「正解ばかり選んできた」という言葉は、親としての私たちに大きな問いを投げかけています。
これからの時代に本当に必要なのは、正解を与えることではなく、子ども自身が気づき・選び・挑戦する力。
そしてその力を支えるのが「視覚機能」と「脳の発達」です。
→あなたは「子どもにとっての正解」をどう考えますか?