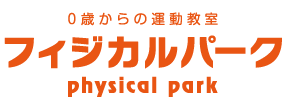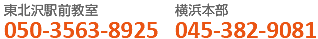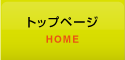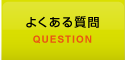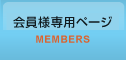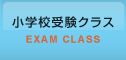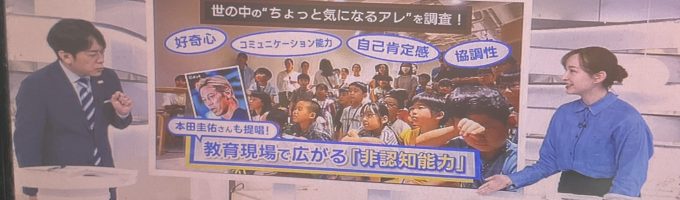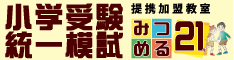数値で測れない力が未来をつくる
最近よく耳にする「非認知能力」。
テストや偏差値では測れないけれど、
子どもの未来に大きく影響する力のことです。
好奇心、自己肯定感、協調性、コミュニケーション力…。
これらは大人になってからも必要とされる
「人としての基盤」。
教育現場でも、この力をどう伸ばすかが
大きなテーマになっています。
本田圭佑選手の取り組み
サッカー元日本代表の本田圭佑選手は、
子どもたちの非認知能力を育む工夫を取り入れています。
彼が発案した少年サッカーの「4v4方式」では、
コーチがベンチに座らず、子ども自身が仲間と作戦を考え、
声を掛け合いながら試合を進めます。
この形式によって育まれるのは――
- 仲間とのコミュニケーション
- 自分で考えて決断する力
- 責任感ややり抜く姿勢
ただサッカーが上手になるだけでなく、
将来に必要な人間力が自然と身についていきます。
教育現場での具体例
学校や学習指導要領でも「非認知能力」
を伸ばす工夫が広がっています。
- 探究学習:子ども自身がテーマを選び、
- 調べて発表する過程で「好奇心」と「自己表現力」が伸びる
- グループワーク:他者の意見を聞き、まとめて発表する中で「協調性」と「コミュニケーション力」が育つ
- 表現活動(演劇や音楽):緊張を乗り越える経験が「自己肯定感」につながる
こうした取り組みは、学力の基盤を支えると同時に、
生きる力をはぐくむ教育として注目されています。
フィジパのメンタルケアとしての非認知能力
フィジパでも運動を通して「メンタルケア」を重視しています。
単なる体力づくりではなく――
- 小さな成功体験の積み重ね → 自己肯定感
- 遊び感覚の課題への挑戦 → 好奇心
- 見え方や動き方を言葉にする → コミュニケーション能力
こうした経験が、子どもの「心の成長」に直結していきます。
毎日の中で「これって大丈夫かな?」と思うこと、
どの親御さんにもあります。そういう時、
ただ検索するだけではなく、相談できる場所があるとホッとします。
フィジパでは、LINEでのやりとりを通して、
お子さんの様子を聞かせていただき、
「どんな時に困っているか」
「どんなことを伸ばしたいか」を一緒に考える場をご用意しています。
強制ではなく、気軽にお話しできることを大切にしています。
➡︎まずはLINE登録から。プロフィールのボタンを押して、
メッセージを送ってみてください。