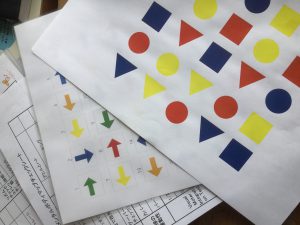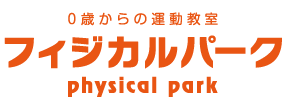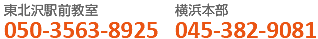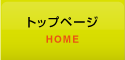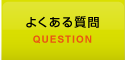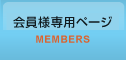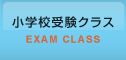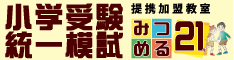「図形になると点数がガクッと落ちる…」
「記述の根拠がどこにあるか見つけられない」
「年表や地図の問題が苦手」
もし、こんな悩みが続いていたら、
それは“勉強の仕方”の問題ではないかもしれません。
実は多くの子どもたちが、「視力は良いのに、見る力(視機能)が弱い」
という課題を抱えています。
今回は、中学受験で問われる“見る力”と、
その背景にある「視機能」の正体について説明しますね。
視力が1.0あっても、見えていない?
視力検査で「1.0」と言われると、
見える力に問題がないように感じますよね。
でもそれは、ただ“止まっているものを静かに見たときの距離感”
を測っただけのもの。
実際の勉強では、
・目を動かして文を読む
・図と問題文を行き来する
・動きの中で細かい情報をキャッチする
こうした“視覚処理”の力が求められます。
これが「視機能(しかきのう)」です。
中学受験で「見る力」が必要になる場面とは?
国語
選択肢を見比べる・記述の根拠を見つけるときに
視線がうまく移動できず、探すのに時間がかかる。
長文になるほど情報の整理が苦手になる。
算数
図形の重なりや回転のイメージがしづらく、
途中式を見落としてミスが出やすい。
条件整理型の問題で情報が整理できず、混乱してしまう。
理科
実験の流れ図やグラフを見ても、変化の傾向がつかめない。
図・表・文章の照らし合わせが苦手で、複数情報の処理が追いつかない。
社会
地図や年表を読むときに、情報をうまく拾えない。
位置関係や時系列がごちゃごちゃになってしまい、
資料問題で不正解が多くなる。
「見る力が弱い」と言われても、見た目にはわからない
視機能の弱さは、眼科ではわからないことがほとんどです。
視力が良いから問題ない、と言われても、
目(視線)の動き・焦点合わせ・空間の捉え方などに
課題があるケースはとても多く、見た目には気づかれません。
そのため学校や塾では「集中してない」「読み飛ばしてる」「理解力が低い」と誤解されてしまうことも。
本人の努力不足ではなく、目の使い方がうまくいっていないだけという可能性もあるのです。
フィジカルパークでは“視機能チェック”からスタートします
フィジカルパークでは、13年間で多くの受験生や
就学前の子どもたちと向き合ってきました。
「図形ができるようになった!」
「読解で選択肢がちゃんと見分けられるようになった!」
そんな声をいただく背景には、
見る力に着目した独自の視機能トレーニングがあります。
-
専門家監修のビジョントレーニング
-
オンライントレーニングでもサポート
-
体の動きと視覚処理をつなぐ運動プログラム
受験をサポートするのは、知識だけではありません。
「見える」「わかる」「自信がつく」
そのプロセスを一緒に育てていきます。
見る力、気になる方はまず相談を
「もしかしてウチの子も…?」
そう思ったら、まずは無料相談でお話してみませんか?
LINEから簡単に相談予約が可能です。
「ちょっと気になって…」くらいの気持ちでOKです。
▼無料LINE相談はこちら